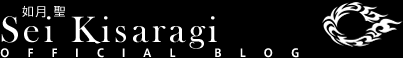レオナルドダヴィンチの幼年期の思い出(フロイト引用)
レオナルドダヴィンチ(1452−1519年)は、イタリア.ルネサンスの最も偉大な人物の一人として、すでに当時の人々から賞賛されていたが、その一方ですでに同時代人にも謎めいた人物と映っていた。これは今もって変わらない。この(ただ輪郭がぼんやりと感じ取られるだけで、決して究めつくしえない)万能の天才が、自らの時代に対して最も決定的な影響を及ぼしたのは、画家としてであった。レオナルドの中では、自然科学者であるということが芸術家としての在りようと結びついていたが、この自然研究者(および技術者)としての彼の偉大さを認識することは、今日にしてようやく取組みうる課題としてわれわれに残された。彼は絵画において数々の傑作を遺したが、その一方で彼が行った科学上の様々な発見は公にされず、またその価値が検討されることもなかった。とはいえ、彼の発展の過程において、自然研究者としての束縛が芸術家としての彼を全面的に開放することはついぞなかった。むしろ往々これをはなはだしく損ない、ついには抑え込んでしまったかもしれない。ヴァザーリのこの話は、外的にも事実ではあるまいし、内的にも大した真実味を持たず、この謎めいた巨匠をめぐって生前に生じ始めていた伝説の類いに属するものであるとはいえ、この時代と、そこに生きた人々による判断の証として持つ価値は否定できない。
なぜレオナルドという人物は同時代人に理解されなかったのだろうか。多才で博識だったレオナルドは、そのお蔭で、自ら改良した楽器を携えてリュート奏者としてミラノ公ルドヴィーコ.スフォルツァ、通称イル.モロの宮廷に地位を得、またこの公爵に宛てた注目すべき書簡の中で建築技師および軍事技術者としての自分の業績を誇らしげに語ることもできたのだが、同時代人から理解されなかったのは、多岐にわたる彼のこの才能と知識のゆえではない。ひとりの人物がこのように多彩な能力を発揮することは、ルネサンスの時代には稀ではなかったからである。とはいえ、レオナルドは、その類いの中でも最も輝かしい例のひとつだった。また彼は、自然からは外見的に貧弱な身体しか恵まれず、当人としても人生の外見上の姿形にはなんらの価値も置かず、痛ましいまでに陰鬱な気分の中で人との付き合いを避けるといった、一部の天才的な人間にありがちな類型に属してもいなかった。むしろ彼は背が高く、均整のとれた体つきをしており、眉目秀麗で、並外れ、人と接する作法も至って魅力的で、話術に長け、誰に対しても朗らかで愛想がよかった。彼は、身のまわりにあるものについても美しさを愛した。派手な衣装を身にまとい、生活の上でも何につけ洗練されていることを重んじた。こうした彼の晴れやかな嗜好を示す、絵画論の中にある一節で、レオナルドは、絵画をその姉妹と言うべき様々の芸術と比較し、彫刻家の仕事の苦労について述べている。(彫刻家は、そこで顔をひどく汚し、大理石の粉をかぶり、まるでパン屋のような具合だ。小さな大理石で幾重にも覆われるので、背中は雪が降りかかったようになり、住まいときては石のかけらと埃にまみれている。これが画家だと何もかもがその逆だ。
...画家は、結構な服を身にまとい、くつろいで自分の作品の前に座って、典雅な絵の具を含ませたごく軽い絵筆をわずかに動かすだけでよいからだ。衣装でもって、画家は自分を好きなように着飾れるし、住まいは晴れやかな絵で満ち、輝くように清潔だ。しばしば、音楽の集いや様々な美しい作品の朗読会を催したりするが、それらに耳を傾けるにあたって、ハンマーの轟音やそのほかの騒音に妨げられることもなく、大いに楽しむことができる。
とはいえ、輝くように朗らかな享楽家としてのレオナルドという見方は、この巨匠の人生の、最初のほうの比較的長い一時期についてしか適当でないのかもしれない。ルドヴィーコ.モロの支配が衰えて、レオナルドも自分の活動圏であったミラノや確かな地位を捨てることを余儀なくされ、フランスで最後の隠棲の地を見出すまで、定かならず外的な成功にも恵まれない生活を強いられた。このころから彼の気分の輝きが色褪せていき、彼の気性に備わる様々の奇怪な傾向がいよいよ強く立ち現れてきたらしい。また年を追うごとに彼の関心の重点は芸術から科学へと移っていったが、これもレオナルドという人物とのあいだの溝を否かにも広げる一因となった。そのころの彼は、例えばかつての弟子仲間であったペルジーノのように注文に応えてせっせと絵を描いて富を得る代わりに、当時の人々にしてみれば時間の浪費にすぎない様々の実験的な試みに手を染めていたが、それらは人々にはすべて気まぐれな遊び事と映り、またそのせいで彼は黒魔術に仕えているのではないかとの疑いさえかけられた。残された手記からレオナルドがどのような技術や芸術を試していたかを知るわれわれは、その点で、彼のことがもっとよく分かる立場にある。当時は教会の権威が古代の権威に座を譲り始めたばかりで、無前提の研究など誰の頭にもなかった時代であるから、ベーコンやコペルニクスの先駆けであるだけでなく、ライヴァルとして彼らに匹敵しえたであろうレオナルドが、孤独へと追いやられていったのは無理からぬことであった。馬や人間の屍体を解剖する。飛行装置を組み立てる、植物の養分を調べては解毒の効用を研究する、そうした試みは、もとより彼を、アリストテレスの注釈者たちからは遠くかけ離れ、むしろ当時蔑まれていた錬金術師たちに近い者としたのだった。実験的研究は、この不遇な時代には、そういった錬金術師たちの実験室の中に逃げ入ることでかろうじて命脈を保っていたのである。
その結果として、彼は絵筆を手に取ることを厭うようになり、次第に絵を描くことが少なく稀になっていった。手がけたものもその大半は未完成のままに放置し、自分の作品のその後の運命について頓着することはほとんどなかった。こうしたことがまた、芸術に対する彼の関係が謎と映った同時代人の非難の的となった。
後世のレオナルド賛美者たちの中には、移り気という汚点を彼の性格から抹消しようと試みる者もいた。いわく、レオナルドの欠点として非難されるものこそ、偉大な芸術家に共通する特性だ。精力的で必死になって仕事をこなしたミケランジェロとて、作品の多くを未完成のままに残したではないか。そのことでミケランジェロが咎を受けないのであれば、レオナルドとて同じはずだ。加えて、レオナルドの絵のかなりは、本人が言明するほど未完のままでもない。素人にはすでに傑作と思えるものも、芸術作品を創造する者にとっては、所詮、自分の意図をいまだ十分に体現せぬものでしかない。彼の年頭には一つの完全があって、それを模造で再現しようとして、そのたびに気後れするのだ。しかし、自分の作品を最終的に見舞う運命に対して芸術家に責任を負わせることなど、およそ筋違いではないか、云々。
如月eye。偉人、レオナルド.ダヴィンチのフロイトが生い立ちや細かく精神分析をしている。この時代では飛び級で逸脱した才能を持ち、周りとのレベルの違い過ぎで、後世になって認められることになった。彼はなぜ人体にこれほどまでに執着したのだろうか。
フロイトは彼の心理面を重点的に分析しているのだが、多才であり、レオナルド.ダヴィンチが生涯に求めたものは何なのか、不思議である。
続く。