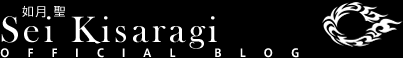不安と欲動生活。(フロイトの論文から抜粋)長編
1、不安については、これまでの一連の講義の第25回目ですでに、テーマにとりあげました。とりあえず、その内容をかいつまんで振り返っておく必要があります。そこで述べましたのはまず、不安とは、一つの情動状態、つまり、快、不快の系列のある度合いの感覚と、この感覚に見合った放散のための神経支配ならびにその感知とが一つになった状態のことをさすのですが、おそらくは、何らかの重大な出来事が遺伝を通じて体内化された澱のようなもので、喩えるなら、各人それぞれが獲得したヒステリー発作にでも匹敵するだろう、といったことでした。私たちは、この種の情動痕跡を残した重大な出来事として、出産という出来事をつけました。
不安に特有の心拍と呼吸の変動は、もともと出産の際にこそ目的にかなったものだったからです。つまり、原初の不安というものは、何か中毒性のものだったのだろうということです。こうした前提のもと、私たちはまず、現実不安と神経症的不安を区別することから出発しました。前者の現実不安は、危険に対する反応、すなわち予期された外部からの侵害に対する反応として、すんなり理解できるのですが、後者の神経症的不安は、いかにも謎めいていて、何のためのものか分からないものです。私たちは、現実不安を分析してこれを感覚的注意力と運動緊張の高まった状態として結論づけ、この状態を不安準備と呼びならわします。この不安準備が不安反応へと発展してゆくわけですが、この不安反応の結末には二種類のものがあります。一つは、あの古い外傷的体験の反復である不安増長が、いわば信号としてのみ働く場所で、その場合には、それ以外の反応は、危険状況が新たに膨らんでくるのに合わせて、逃亡や防御の手を打つといった結末にいたります。
もう一つはあの古い外傷体験が圧倒的になり、反応全体が不安増長で尽きてしまう場合には、この情動状態は、全身の力を萎えさてしまうため、逆に現在の状況にとってよろしくない結果となってしまうのです。つづいて私たちは、神経症的不安に目を向け、これには三つの異なった事態が観察されることをご報告いたしました。一つは、自由に浮揚しどんなものにも向けられる危惧で、新たに浮上してくるどんな可能性とも次々手当たり次第に結びつくため、いわゆる予期不安と称するべきもので、例えば典型的な不安神経症に見られる類いのものです。もう一つは、いわゆる恐怖症にみられる、特定の表象内容にしか結びついた不安でして、この場合、外的危険とのある種の結びつきはなんとか認められはしますものの、これに対する不安が度を越えて誇張されているとしか思えません。最後の三つ目は、ヒステリーや他の形態の重度の神経症に見られる不安で、もろもろの症状にともなって現れる場合も、単独で現れるもあり、発作の形をとるかと思えば、慢性的な形をとったりもしますが、いずれの場合も、何らかの外的危険によってもはっきり理由づけることができない点を特徴とするものです。
このように見てきた結果、私たちとしましては、次のような二つの問いを提起せざるをえなくなったわけです。すなわち、これら神経症的不安は、外的危険に向けられた現実不安とどういう関係にあるのかという問いです。
私たちの研究は決して無駄には終わりませんでした。重要な解明がいくつか手に入りました。不安に満ちた予期に関しましては、臨床上の経験から、これがいつも性生活におけるリビード家政に関係していることが判いたしました。つまり、不安神経症のもっとも普通の原因は、フラストレーションに終わった興奮だということです。リビードの興奮が引き起こされても、それが満足させられず、使用もされないような場合、この使用に供されなかったリビードに代わって、びくびくした不安感が出現するわけです。私には、この充足させられなかったリビードがそのまま直接不安に変化すると言い切ってよいとも思えたほどです。
これら子供の恐怖症というものは、私たちには極めて謎めいたものが多いのですが、そうではなような恐怖感、例えば一人きりにされた時の不安だとか人見知りのような不安は、はっきり説明が可能なのです。つまり、一人きりにされたり、見知らぬ顔が現われたりしますと、それによって幼児は、親しんだ母親への切ない思いを掻き立てられ、このリビード興奮を抑えることも浮揚したままにしておくこともできないで、これを不安に変えるということです。この幼児不安は、したがって、現実不安に属するものではなく、神経症的不安の一つということです。この幼児期恐怖症、ならびに不安神経症の不安予期は、神経症的が生じる一つの方式を説明する二つの好例とも言えます。すなわち、リビードが不安へと直接的に変換されることによるということです。神経症的不安のもう一つの規制も、すぐにい知れます。それは、この第一の規制とさほど違ってはいないのです。
私たちは、ヒステリーやその他の神経症に見られる不安は、抑うつという出来事によるものだと考えております。この抑圧という出来事を、これまでよりも完全な形で記述するには、抑圧されるべき表象の運命と、その表象に付着しているリビード量の運命を別々に切り離して扱う必要があります。抑圧を受けて、ともすると見分けがつかなくなるほど歪曲されるのは、表象の方です。これに対して、表象がもっている情動量のほうは、不安に変わるのが通例です。しかも、その情動の種類が攻撃的なものであれ、そうしたこととは無関係に、情動量は不安に変わるのです。加えて、あるリビード量がどのような理由で使用されないままになったのかということも、本質的な違いを作りません。幼児期恐怖症の場合のように自我の幼児期的な弱さからくるのであれ、不安神経症の場合のように性生活における肉体的出来事(リビード鬱積)の結果であれ、あるいは、ヒステリーの場合のように抑圧によるのであれ、本質的な違いはありません。つまり、神経症的不安の発生の二つの機制は、もともと同じだということなのです。
このような探求を続けている中で、私たちは、不安増長と症状形成の間に極めて重要な関係があることに注意を向けるようになりました。すなわち、両者は互いに代行しあい、交代しあうということです。例えば広場恐怖症患者の場合ですと、その一目瞭然病歴の開始点にくるのは、路上での不安発作です。再び路上に出ようものなら、その度に、この発作が繰り返されることになりかねません。そこで患者は、自我による制止ないしは自我による機能制限とも呼ぶことのできる路上不安という症状(広場恐怖症)を形成し、それによって不安発作を逃れるのわけです。これとは逆のことも見られます。例えば強迫行為などの際によく起こることですが、症状形成に何らかの干渉が加えられたような場合がそうです。
洗浄儀式を行うのを妨げたりしますと、患者は耐え難い不安状態に陥るのです。ここからはっきりしますのは、それまで症状が患者をこうした不安状態にならないように守っていたということです。付け加えさせていただきますと、どうやら、不安増長のほう先、症状形成が後であるらしく、不安状態の勃発を回避するために症状が形成されるようなのです。幼児期に起こる最初の神経症であるという事実も、このことを裏付けております。この幼児期の恐怖症の状態を見れば、先にまず不安増長があって、これが後に症状形成にとって代わられることは人目瞭然なのです。
続く。
如月eye
神経症に大きな功績を遺したフロイトの神経症への研究は、現在もその分野では生きていますが、ここまで内側からアプローチできたのは、天才しか他ないでしょう。
ここでいうリビード、現在はリビドーとも名づけられています。
不安と欲動生活はまだまだ続きます。