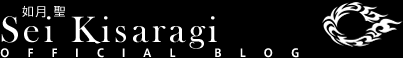戦争はなぜに?(フロイトの論文から抜粋)④
私たちは人間の欲動には二種類しかないと想定しております。想定一方には、維持し統合しようとする欲動群で、私たちはこれらを、プラトンの(饗宴)に出て来るエロースそのままの意味でエロース的な欲動、あるいは通俗的な性の概念を意識的に広げて性的欲動と呼んでいます。もう一方は、破壊し殺害しようとする欲動群で、私たちはこれらの欲動を攻撃欲動ないし破壊欲動という名で概括しています。
これが本来は世間に周知の愛情の対立を理論的に洗練したものにすぎないのはご覧のとおりです。ちなみに、この愛情の対立は、ご専門の分野で一定の役割を果たす引力と斥力の双極性と何か根源的な関係を持っているのかもしれません。さて、性急に善悪の評価を持ってくるのは控えましょう。これら二つの欲動野の内にいずれもが必要不可欠なのです。両者が協働したり対抗しあったりする中から様々な生の現象が生じてきます。
そうして、一方の種類に属する何か一つの欲動だけが単独で活動しうるなどということは、ほとんどないように思われます。欲動は常にもう一方の側のある一定量と結合しています。ちなみに、私たちはこれを混晶化している。と言っております。そのせいで、欲動の目標に変更や修正が加えられたり、あるいは場合によっては目標の達成が初めて可能になったりします。だから、たとえば自己保存欲動は、確かにその本性がエロース的なものとはいえ、自らの意図を貫徹することになるなら、それ自身、攻撃性を備えている必要があるのです。
同じように、対象に向けられた愛の欲動も、そもそも自らの対象を手に入れようというなら、征服欲動の援軍を必要とするのです。二つの欲動の種類を、それらの発現している状態において分離することは難しく、これに妨げられて、私たちも実に長い間これらの欲動を認識することができませんでした。この先、もう少し私に付き合って頂けるなら、人間のもろもろの行動には、さらにこれとは別種の合併、複雑化が認められるということについてお話しましょう。
行動がただ一つだけの欲動の蠢きの所産であることはごく稀です。欲動の蠢きそのものがそれ自体すでにエロースと破壊性とから合成されているに違いありません。通常、行為が可能となるためには、複数のそれぞれ同じように構成されている動機が出会う必要があります。あなたと同じ専門分野の先達であるゲオルク.クリストフ.リヒテンベルク教授のような人は、すでにこのことを意識していました。彼はわが古典主義の巨匠たちが活躍した時代にゲッティンゲンで物理学を講じていましたが、ことによると物理学者としてよりも心理学者としてのほうが重要であったと言えるかもしれません。
リヒテンベルクは、次の発現に見られるように、動機の羅針盤というものを考案しました。(人が何かをするときの運動根拠は、32万位と同じように整理することができ、その名称も例えばバン、バンとか、名声、名声、バンといった具合に風向きと似たような形で定式化することができるだろう)。したがって、戦争に馳せ参じるよう促されようものなら、人間の中にあるあまたの動機が戦争に賛同の声をあげることでしょう。気高い動機に卑しい動機、声高に語られる動機もあれば人には言えない動機もあります。私たちは何もこれらすべてをさらけ出すいわれはありません。
攻撃と破壊に興じる快は、間違いなくそういった動機の一つであり、歴史上の、あるいは日常の数えきれない残虐行為は、これらの動機が存在し、またいかに強力であるかを裏付けています。この破壊追求が別の追求、例えば性愛や理念の追求と混こうすると、当然、満足が得られやすくなります。
歴史上の蛮行を耳にするとき、理念的な動機は破壊的な情欲によって単に口実として利用されたにすぎないという印象を受けることがままあります。別の場合にはまた、たとえば異端審問における残虐行為はでは、もろもろの理念的な動機が意識の前面でわれ先にひしめく一方、破壊的な動機がそれらに無意識に加勢していると思われたりもします。いずれもありえます。
続きます。